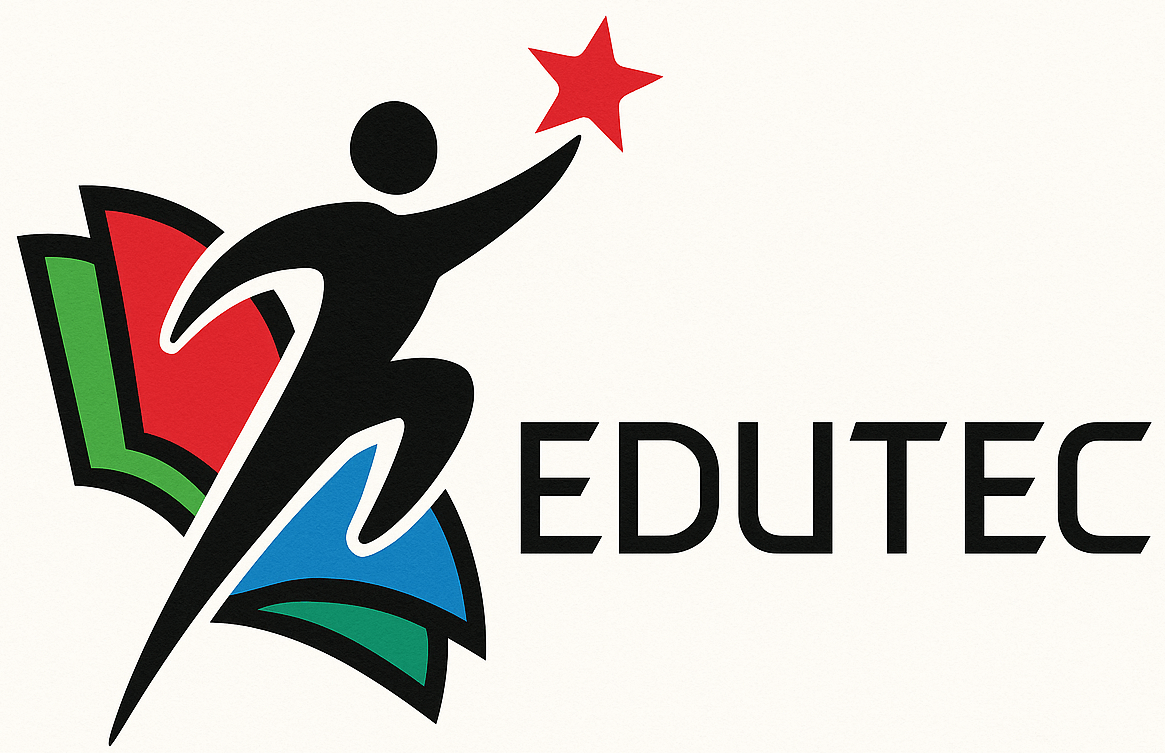読み聞かせは、単に物語を楽しむだけでなく、子どもの論理的思考力や想像力を育む絶好の機会です。特に、「次はどうなると思う?」と問いかけたり、「なぜ〇〇は△△したのかな?」と登場人物の行動理由を考えさせたりすることは、物語への深い理解を促し、多角的な視点を養う上で非常に有効です。
なぜこれらの問いかけが重要なのか?
これらの問いかけが重要である理由はいくつかあります。
- 因果関係の理解促進: 物語の中の出来事には、必ず原因と結果があります。登場人物の行動や物語の展開について考えることで、子どもは自然と因果関係を把握する力が養われます。
- 推論能力の向上: 物語の断片的な情報から、次に起こることを予測したり、見えない登場人物の感情や思考を推し量ったりする力(推論能力)が高まります。
- 多角的な視点の育成: 「もし自分が〇〇だったらどうする?」と問いかけることで、登場人物の立場に立って考える機会が生まれ、共感力や多角的な視点が育まれます。
- 表現力の向上: 自分の考えを言葉にして説明する練習になり、表現力やコミュニケーション能力が向上します。
- 物語への没入感の深化: 能動的に物語に関わることで、受け身で聞いているだけの場合よりも、物語への興味や関心が深まります。
具体的な問いかけの例と解説
1. 物語の展開を予想する問いかけ
物語の途中で一度読み聞かせを中断し、「この後、どうなると思う?」と問いかけます。
例1: 『3びきのこぶた』の場合
- 問いかけ: 「狼が『わらの家』を吹き飛ばしちゃったね。次、子ぶたはどうすると思う?」
- 子どもの反応の例:
- 「もっと丈夫な家に逃げる!」(既知の情報から推測)
- 「お母さんのところに帰る!」(感情移入による想像)
- 「狼をやっつける!」(願望による想像)
- 大人の対応: 「なるほど、そういう考え方もあるね。どうしてそう思ったの?」と、子どもの考えの根拠を尋ねることで、推論のプロセスを深めます。その上で、「絵を見ると、次はあそこに向かってるみたいだよ?」など、ヒントを与えても良いでしょう。
2. 登場人物の行動理由を考える問いかけ
登場人物が特定の行動をとった場面で、「なぜ〇〇は△△したのかな?」と問いかけます。
例2: 『うさぎとかめ』の場合
- 問いかけ: 「どうしてウサギはカメと競争したのかな?」
- 子どもの反応の例:
- 「ウサギがカメのことバカにしたかったから!」(登場人物の感情の推測)
- 「自分の方が速いって見せつけたかったから!」(自己中心的な動機の推測)
- 「カメが挑戦してきたから!」(相手の行動への反応と考える)
- 大人の対応: 「そうだね、ウサギは足が速いから自信があったんだね。でも、カメはどう思ったかな?」と、別の登場人物の視点に立って考えさせることで、共感力を育むことができます。
例3: 『赤ずきん』の場合
- 問いかけ: 「なぜオオカミはおばあさんに化けたの?」
- 子どもの反応の反応:
- 「赤ずきんちゃんを騙したかったから」
- 「赤ずきんちゃんを食べたかったから」
- 大人の対応: 「そうだね、オオカミは赤ずきんちゃんを食べようとしたんだね。もしオオカミがそのままの姿だったら、赤ずきんちゃんはどうしたかな?」と、別の可能性を考えさせることで、物語の展開の多様性や登場人物の行動の意図をより深く理解させることができます。
これらの問いかけは、子どもが物語の「原因」と「結果」、そして「登場人物の思考・感情」の繋がりを理解するのに役立ちます。